
スクラップ&ビルドから、ストックへ。島原万丈さんが問い直す、住まいと生き方の自由
LIFULL HOME'S総研所長の島原万丈さんに、今なぜストック型社会への転換が求められているのか、リノベーションという営みの本質、住むことの自由とこれからの「暮らし」について、お話を伺いました。
1989年株式会社リクルート入社。2005年よりリクルート住宅総研へ移り、2013年3月リクルートを退社。同年7月、LIFULL HOME’S総研所長に就任。主な著書に『本当に住んで幸せな街 全国官能都市ランキング』(光文社新書)がある。
「DoboX」で地形を見る

ふと気がつくと「リノベーション」という言葉が、とても身近なものになりました。住まいを選ぶ際にも、「リノベ住宅」という選択肢が、ごく自然に受け入れられるようになっています。
LIFULL HOME’S総研が発表した『STOCK & RENOVATION 2024』は、そんなリノベーションという概念の浸透を前提に、それが既存住宅流通市場の活性化やストック型社会への転換をどの程度まで推し進めたのか、あるいは人びとの住むことの自由をどれほど拡張したのかを問う、意欲的な調査研究書です。
「それでも、もっと住むことの自由」という副題を掲げた本書の問いかけは、広島での「暮らし」を考えるうえでも、きっと大きな手がかりになるはずです。
そこでお話を伺ったのが、LIFULL HOME’S総研所長の島原万丈さん。今なぜストック型社会への転換が求められているのか。リノベーションという営みの本質とは。そして住むことの自由は、私たちの暮らしに、どう関わってくるのか。常にロジカルでありながらも、静かな熱を帯びた島原さんの言葉に、耳を傾けてみましょう。
島原さんが手がけた『STOCK & RENOVATION 2024』は、以下のリンクから無料で閲覧いただけます。
『STOCK & RENOVATION 2024 それでも、もっと住むことの自由』(LIFULL HOME’S総研)
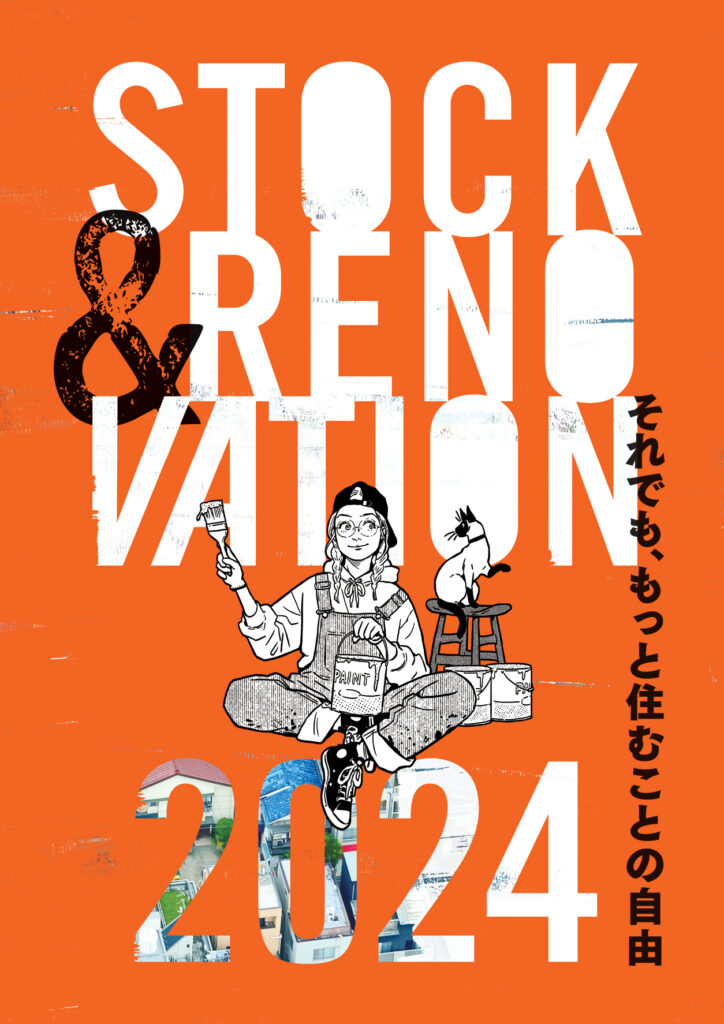
ストックとしての住宅を活用することで、
豊かさを手に入れよう
——島原さんたちが手がけた『STOCK&RENOVATION 2024』を、興味深く読ませていただきました。あの本のキーワードのひとつである「ストック型社会への転換」という問題意識について、まずは改めて教えてください。
島原さん:端的に言うと、これまでつくられた建築物というのは、すべて「ストック」なんです。個人の住宅だけに限らず、たとえば、ビルもそうですし、道路や橋といった公共インフラもストックだと捉えられます。これらを循環的に活用することで、みんなで豊かさを手に入れましょう、というのが私たちの基本的な提案です。
——逆にいうと、これまでの日本社会は、ストックを十分に活用できていなかった?
島原さん:そう思います。ストック型社会の反対は、スクラップ&ビルドを前提としたフロー型の社会です。住宅に関していえば、これまでは年間にどれだけの新築住宅を建てるか、ということで経済を計ってきた。住宅着工数が多いのがグッドニュースで、それが少なければバットニュース、といった具合です。でも人口は減っていて、空き家の増加も問題になっているのに、経済のために新たな住宅をどんどん建てていこうというのは、ちょっとおかしな話ですよね。
——矛盾していますよね。ちなみにストックを活用することのメリットを、もう少し教えてもらえますか?
島原さん:既存の住宅というのは、当然ながら建設投資は既に終わっています。あとは適宜リノベーションだけをすればいい。要するに、ストックを活用する方が、コストがかからないわけです。そしてそれは、建設にかかるエネルギーを抑制することにもつながっています。つまり、環境にかける負荷も少なくなる。この2つが、まずは大きなメリットです。

「日本人は新築が好き」は、
戦後の経済成長が生み出した幻想だった?
——すごくまっとうでポジティブな提案だと思う一方で、「新しいものをつくりたい」と考えるつくり手には、ちょっと酷な話かもしれないな、とも感じたのですが、その点はいかがですか?
島原さん:たしかに、建築の世界で働く人のなかには「自分のクリエイティビティで、イチからモノをつくりたい」と思っている人もいるでしょう。それはわかるし、否定するつもりもありません。ただ、世の中のニーズは明らかに変わってきている。だったら、クリエイティビティの発揮の仕方を、今あるものをどうやって活用していくのか、という方向にチェンジしていくほかない。世界的に見ても、一部のスター建築家を除けば、多くの建築人材が、ストックの再生・活用をメインフィールドするようになっています。
——なるほど。そうなると、消費者も意識を変える必要がありそうですね。
島原さん:ひと昔前までは、「日本人は新築が好き」と言われている時代もありました。けれどポイントは、平均的な日本人が、新築の持ち家を買うことが当たり前だった時代というのは、戦後のほんの一時期だけだった、ということです。
——そうなんですね。ちょっと意外でした。
島原さん:戦前、あるいは江戸時代の日本人というのは、ほとんどみんな借家で暮らしていたわけです。新しい住宅を建てることがあるとすれば、その多くは地震や火事によって、住宅が失われてしまった場合です。新しい家がほしいから建てる、なんて発想は、日本人にはあまりなかったはずです。

どういう家で暮らすかは、
思想や生き方にもつながっている
——「ストック型社会」に移行していくために、課題はどこにありそうでしょうか?
島原さん:まずは制度の問題が大きいと思います。これまでの日本の住宅行政は、新築を建てることに対して、強いインセンティブを設けてきました。新築を購入したときの方がローン減税も大きいし、再開発のタワーマンションに至っては、事業費の30%近くを補助金で賄っている、というケースもざらにあります。そして、転売目的や相続税対策としてタワーマンションを買う人も少なくありません。
——それがフロー、つまり新築を建てることを助長してきた部分があるわけですね。
島原さん:最近は、中古物件やリノベーション物件も、銀行の住宅ローンに組み込めるようになってきたりもしているのですが、まだまだ新築が優遇されているのが現状だと思います。まずはここを変えていくべきでしょうね。
——なぜ新築がそこまで優遇されてきたのでしょうか?
島原さん:そもそも、国の大きな方針として、「国民に自分の住宅を持たせよう」という方向性があったんです。住宅を持つことが国民の資産形成にもなり、それが国の復興になり、ひいては社会の安定化につながるからです。実際に、自分が住宅をはじめとした資産を所有していたら、社会の転覆なんで望まないじゃないですか。
——たしかに、そうですよね。
島原さん:これは日本をはじめ、西側の先進諸国に共通するひとつの傾向です。ちなみにフランスやドイツ、北欧のようにリベラル寄りな価値観が根付いた国だと事情が異なり、賃貸住宅の比率がもう少し高くなってくる。言い換えると、どういう家に住むかということは、実は思想や生き方とも関係しているんです。
——すごく面白い視点ですね!
島原さん:ただ、今の日本では、新築というかたちで国民に資産を持たせることが、どんどん難しくなってきています。都市部のマンションを中心に、不動産の資産価値が一気に上がり、それに賃金の上昇が追いついていない。それどころか、不動産価格の上昇に釣られ、その周辺の賃貸物件の家賃までもが上がってしまい、多くの人々の暮らしを圧迫しています。だから「国民に資産を持たせる」という方針を維持するのであれば、やはり中古物件やリノベーション物件といったストックを活用するほかない。国としても、そのために補助金や税金を使うべきだと思います。新築については、建てたい人が趣味や道楽として建てれば、それでいいはずです。

リノベーションの本質は、
空間に「意志」を込めること
——ストック型社会の実現に向けて、私たち消費者としては、具体的にどのような意識を持てばいいのでしょうか?
島原さん:海外の市場を調査していると、日本の消費者はかなり特殊だなと思うことがあって。家を買うとき、特に新築を購入するときは、神経質なまでに「完璧」を求めるんです。それこそ壁紙のちょっとした傷も許さない。けれど不思議なことに、一度それを手に入れてしまうと、メンテナンスや維持管理には、とたんに無頓着になってしまう。海外では反対で、購入するときは傷なんて全然気にしない。「気に入らなかったら、自分で直せばいい」という発想が自然と根付いているんです。このマインドは、日本の消費者も見習った方が、よりハッピーに暮らせるのにな、と思っています。
——そういうライフスタイルを、島原さんは「マニュアルミッション」と表現されていましたね。
島原さん:やっぱり今は、住宅に限らず「それなりの商品を、安く手軽に買いたい」という人が多いじゃないですか。オートマどころか、自動操縦を求めている節さえある。一概に悪いこととは言えませんが、それだけじゃあ面白くなくないよな、と私は思うんです。実際に、あれこれ考えながら手を動かして、自分の家をリノベーションした人って、幸福度がすごく高くなるんですよ。
——考えてみると、家って、人生のなかで一番長い時間を過ごす場所ですもんね。
島原さん:そうなんです。だからリノベーションの本質というのは、家という空間に自分の「意志」を込めることだと思っていて。その過程では「壁紙の色はこれでいいんだっけ?」とか、いちいち悩むわけです。でも、それはつまり「自分はどういう空間で、どういう暮らしをしたいのか」を考えることですよね。もっと言えば、それは「自分がどういう人間でありたいのか」とも無関係ではありません。つまり、家づくりは自己実現につながるのです。そこを自覚できるようになると、住宅に関する消費者の意識も、もう少し変わってくるのかなと思います。
——そういうマニュアルミッション的な暮らしを実現するためのコツがあれば教えてください。
島原さん:最初からいきなりリノベーションに挑戦する必要はないんですよ。簡単なDIYでもいいですし、もっと言えば壁にお気に入りの絵を掛けてみるだけでもいい。自分がどんな暮らしをしたいかを自由に想像し、小さな実践を積み重ねていくことが大切なのかなと思っています。
——小さな工夫でも、まずは実践してみると、暮らしの景色がちょっと変わってきそうですね。そんな島原さんにとって「暮らし」とは何でしょうか?
島原さん:ありきたりな答えかもしれませんが、日々のなかで選択を積み重ねていく、ということだと思います。いちいち立ち止まっては、自分がどうありたいのかを、自身に問いかけ続ける。いろんな制約があるなかで、一生懸命考えながら、できる限りの自由を追求していくこと。それが結局は、生きていくということなのではないでしょうか。

「DoboX」で地形を見る


