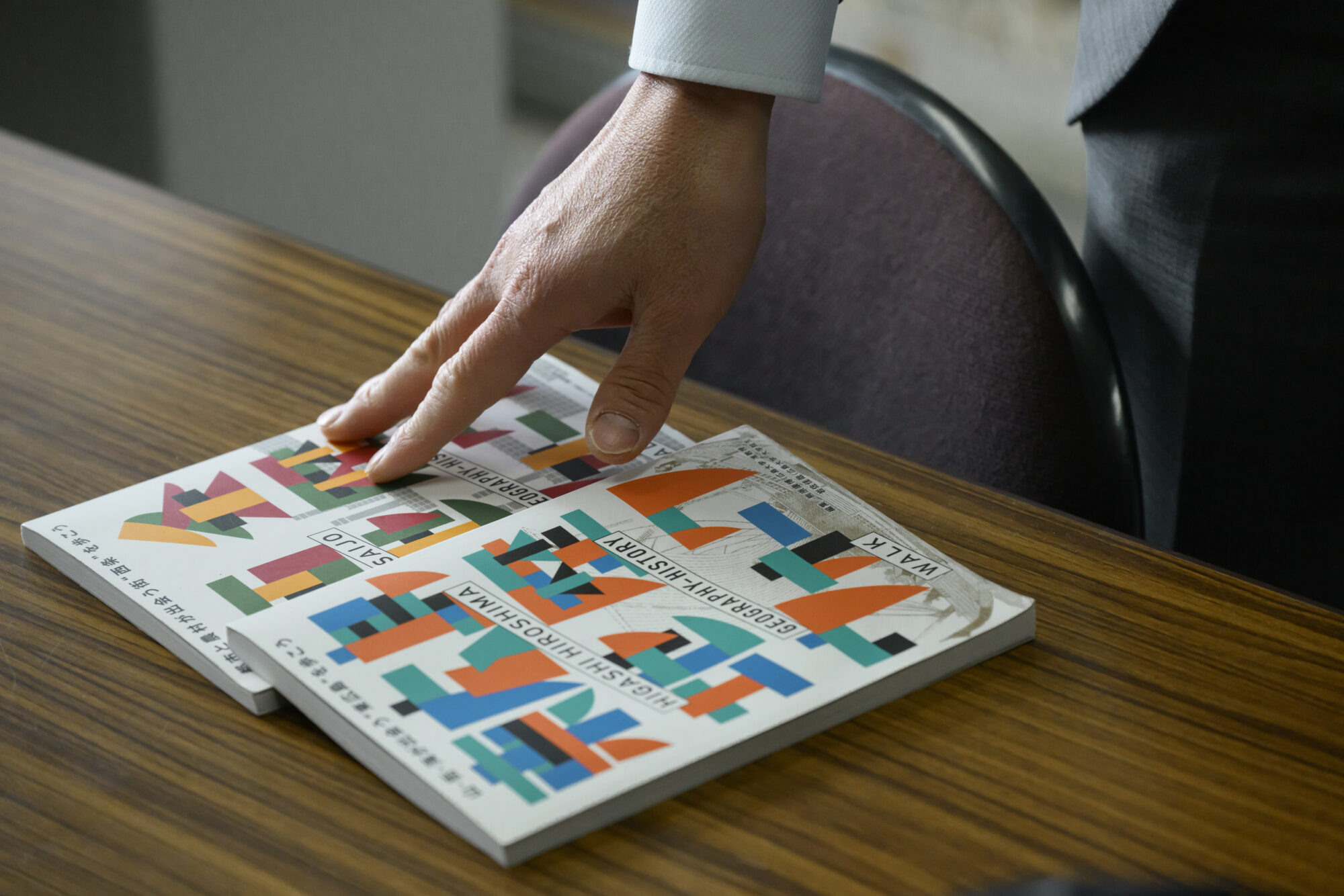広島を「地形」から見つめなおす。広島大学・熊原康博と紐解く、土地と暮らしの歴史
地理学と歴史学を組み合わせ、その土地で暮らしてきた人々の営みを立体的に描き出す。そんな研究に取り組んできた広島大学の熊原康博先生とともに、広島という土地の成り立ちと、そこに刻まれた人々の歴史を紐解きます。
広島大学大学院 人間社会科学研究科 教授。1975年生まれ。広島大学教育学部卒。同大学院文学研究科地理学専攻修了。広島大学総合博物館助教、群馬大学教育学部准教授などを経て、2024年4月から現職。
「DoboX」で地形を見る

私たちの暮らしの、最もたしかな土台となるもの。それはきっと「土地」ではないでしょうか。人も街も、文化も歴史も、ありとあらゆるものは、土地に支えられている。けれど私たちは、日常のなかで、その大前提をついつい忘れがちです。
だからこそ、これからの広島の「暮らし」を考えていくために、まずお話を伺うべきだと思ったのが、広島大学の熊原康博先生でした。地理学と歴史学のアプローチを駆使して、熊原先生が描き出すのは、広島という土地の成り立ちであり、そこで生きた人々の創意工夫の軌跡です。
たとえば、広島の三角州はどのようにして今の姿へと至ったのか。そこに人の営みが、どのように関わっているのか。水とともに生き、時にその力に翻弄されながらも、この土地で生き続けてきた人々の暮らしとは。
広島という土地と、その上に刻まれた人々の歴史を、熊原先生とともに紐解いていきましょう。
地理と歴史を重ね合わせると、
人々の暮らしが立体的に見えてくる
――先生は広島のご出身ですか?
熊原先生:生まれは東京ですが、小学生からは広島で、大学も広島大学です。でも、群馬大学で教鞭をとっていた時期が6年半ほどありました。正直、地理学的には群馬の方が研究しがいがあるんです。火山や大きな川があるから、地形もダイナミックで。広島はどちらかというと、地形的な表情はそれほど豊かじゃないんですよ。だから今日は、いい話ができるか、ちょっと不安です(笑)。
――いやいや(笑)。先生は地理学だけではなく、そこに歴史や文化を絡めた研究もされていますよね。
熊原先生:学生が興味を持ちやすいようにと思ってはじめたのですが、やってみるとこれが面白くて。歴史や文化というのは、実は地理的な条件に大きな影響を受けています。昔の人々にとって、地形というのは制御するのが難しいものだったわけで、だからこそ人々は地形を生かしながら暮らしを営んできた。その創意工夫が、僕にはすごく興味深いんです。
――ぜひ具体例を伺ってもいいですか?
熊原先生:たとえば、東広島市福富町(旧 久芳村・竹仁村)では、どうも大正末期から昭和初期に、村が自前で水力発電所を運営していたらしい。石碑や郷土資料を読めば、そのことはわかります。でも、肝心の発電所の位置が記録されていなくて。そこで地元の人に聞き取りをして、その場所を特定したんです。今でもちゃんと鉄管が残っていました。そこはちょうど、川が急になっているところなんです。
――その水の流れを利用したわけですね。
熊原先生:そうそう。もう少し背景を説明すると、大正デモクラシーの頃、大資本の圧力に対抗して、いかに地域の自立性を確保していくのか、という流れがあったわけです。福富の人たちは、自分たち村の地形を生かして、それを見事にやってのけた。こうやって地理と歴史を重ね合わせると、過去の人々の暮らしが立体的に見えてきますよね。それがこのアプローチの面白いところです。
広島三角州は、
人の手によってつくられた!?
――改めて、広島という土地の地理的・歴史的な特徴についても伺いたいです。
熊原先生:まず大前提として、広島で歴史の研究するのは、すごく難しい部分があって。つまり、原爆の問題ですね。広島市内に集められていた古い史料の多くが、被爆によって失われています。
――そんなところにも原爆の影響があるんですね。
熊原先生:その上でいうと、広島という街自体は、全国的にみればそれほど歴史の古い街ではありません。広島三角州で本格的に街づくりがはじまったのは、安土桃山時代(1589年頃)に、毛利輝元が築城を開始してからと考えられています。それより前の太田川沿いの中心地は、三角州より上流の、今でいう安佐南区祇園のあたりです。
――広島三角州は、どのように形成されたのでしょうか?
熊原先生:縄文時代前期、つまり今から7000年ほど前から、太田川によって土砂の堆積がはじまり、徐々に三角州が形成されていきました。それ以前は、広島市西区大芝のあたりが太田川の河口だったと考えられています。ちなみに広島三角州は、中世以降に急激に拡大しているのですが、その理由についてはひとつの仮説があります。
――どんな仮説なのか、気になります。
熊原先生:中世の太田川上流域は「たたら製鉄」が盛んに行われていた地域です。当時は、鉄の原料となる砂鉄を採取するために、山を人為的に切り崩す「鉄穴(かんな)流し」と呼ばれる手法が用いられていました。このときに生じた大量の土砂が太田川へと流れ込み、三角州を前進させたのではないか、という仮説です。
――人の営みが、そんなに昔から地形に影響を与えていたんですね!
熊原先生:ただ、それを証明するたしかな証拠は、まだ見つかっていなくて。ボーリング調査をすると、中世以降に土砂の堆積が増えていることは明らかなのですが、その要因がたたら製鉄だとまでは、言い切れないのが現状です。
「川の街」の歴史は、
人々が水と向き合ってきた歴史でもある
――地理と歴史のつながりを感じさせるようなものって、探してみれば身近なところにもあったりしますか?
熊原先生:あると思いますよ。たとえば広島市内の水辺には、水運が交通の要だった江戸時代、船着場として機能していた「雁木」と呼ばれる石段が、今も数多く残されています。広島に限ったものではありませんが、これは潮の満ち引きによる水位の変化が多い河川で、スムーズな荷揚げを実現するための、人々の生活の知恵です。
――広島は「川の都」とも呼ばれていますが、やはり昔から河川が人々の暮らしと密接に結びついていたんですね。
熊原先生:そうです。そしてそれは、人々が「治水」に取り組んできた歴史でもあります。第二次世界大戦直後までは、太田川はたびたび氾濫し、数年に一度のペースで広島市内も水浸しになっていました。けれど幸いなことに、昭和42年に現在の太田川放水路が完成してからは、広島市内では水害による大きな被害は出ていません。
――ただ、市内には今も浸水の危険性がある地域がありますよね。
熊原先生:いわゆる「(標高)ゼロメートル地帯」と呼ばれる地域だと、降った雨が排水できず内水氾濫が発生する可能性はあります。やっぱりそれにも歴史的な背景があって。広島では江戸時代から、干潟や海を「干拓」して陸地を広げていきました。さらに明治以降、干拓技術の発展によって、かなり低い土地まで、人が住めるようになってしまった。不安感を煽るわけではありませんが、そういうリスクがあると理解した上で、そこに住むかどうかを判断すべきだと思います。
ぜひみなさんの手で、
地域の暮らしを再発見してほしい
――ちなみに先生自身は、ご自宅を購入される際などに、そういう災害リスクを、入念にチェックされるんですか?
熊原先生:それは大事な質問ですね(笑)。実のところ、僕が住んでいる地域も、浸水の危険性がある地域なんです。その地域のなかでは、少し高いところにあるので、床上浸水はしないと思いますが、床下浸水の可能性はゼロではない。そのリスクを把握した上で、購入した家です。
――ちょっと意外でした! でも、たしかに住まい選びの基準って、いろいろありますもんね。
熊原先生:そうなんです。やっぱり通勤・通学の利便性とか、治安とか、考慮すべき要素はたくさんあるじゃないですか。地形や災害についてももちろん考えますが、それが最優先なわけではありません。それになんと言っても、予算がありますからね。その範囲内で、自分として納得のできる判断をしたつもりです。なんだか、地理とも歴史ともあまり関係のない、生々しい話になってしまいましたね(笑)。
――いえいえ。先生のリアルな実感が伺えて、すごく参考なりました。それではこの流れで、最後の質問をさせてください。先生にとって、暮らしとはなんですか?
熊原先生:うーん、難しい質問ですね。ひとつ言えるのは、これから先の「暮らし」を考えるのであれば、これまでの歴史のなかで、人々がどういう暮らしをしてきたのかを、しっかりと見つめ直す必要がある、ということです。それは私たち研究者だけの役割ではありません。できればみなさん自身が、その地域の地理や歴史について、面白がりながら調べてほしい。それは自分の暮らしに、愛着を持つことにもつながっていくはずです。僕たちも、できることがあればお手伝いします。まずは散歩気分で、地図を持って近所を歩き回ることからはじめてみてはいかがでしょうか。
「DoboX」で地形を見る