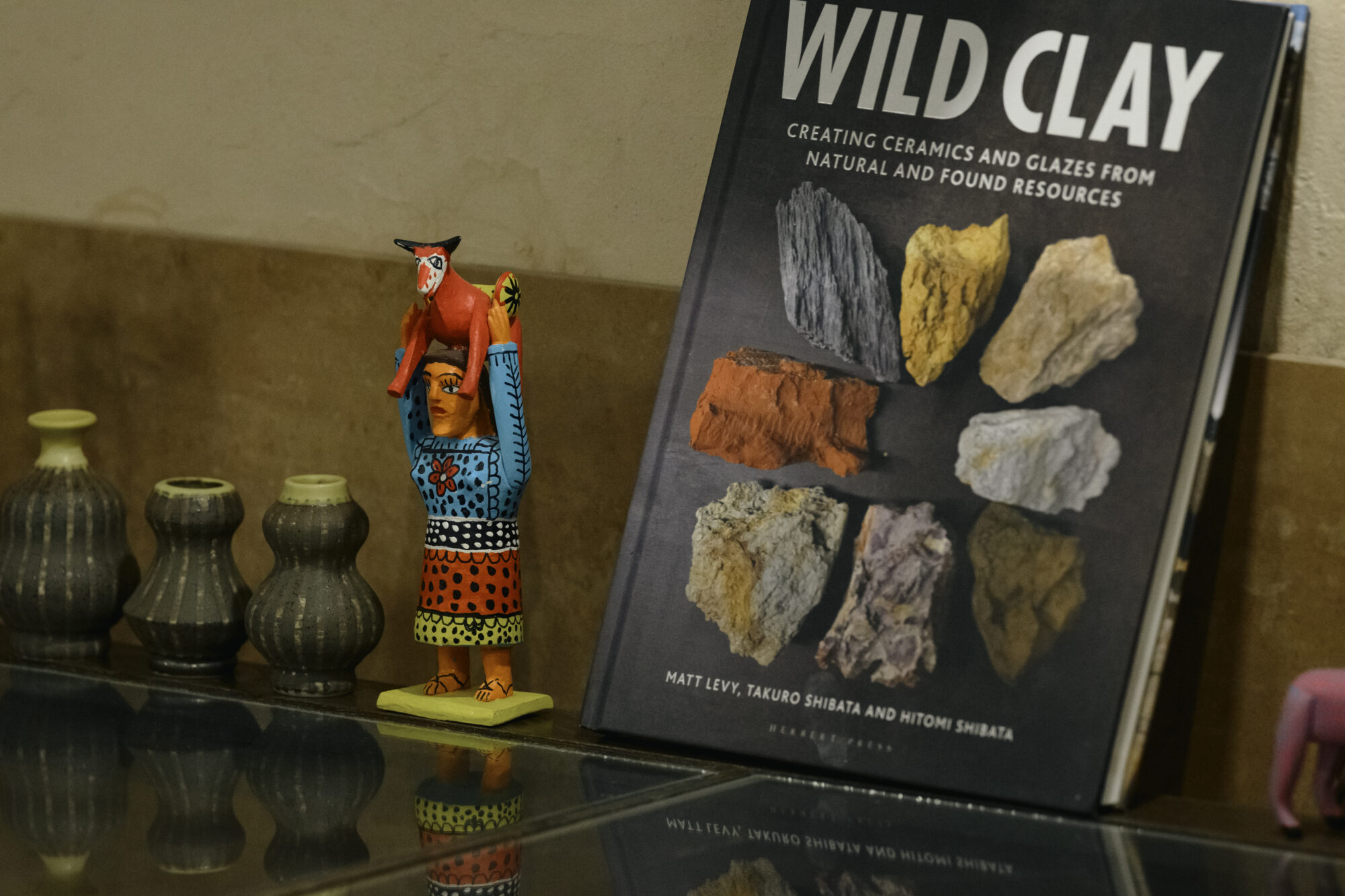自然を原資に、自分を表現する。陶芸家・吉野瞬さんが語る、土と暮らしのこと
広島市西区の地下にあるアトリエで、土と自分とひたすら向き合いながら制作に取り組む陶芸家・吉野瞬さん。自然を原資にものをつくることの醍醐味、作家としての「土地」との距離の取り方、そして暮らしのなかで暮らしの器をつくる陶芸という営みについて、お話を伺いました。
1986年、広島市生まれ。広島市立基町高校創造表現コース卒業後、栃木県益子焼の佐久間藤太郎窯、四代目佐久間藤也に師事。2012年に独立。因島での制作活動を経て、現在は広島市西区にアトリエを構える。2023年のG7広島サミットでは、主要国首脳会議ワーキングディナーにて作品が採用。国内外で積極的に個展を開催する。
「DoboX」で地形を見る

プラスチックや金属、ガラス――。私たちの日常は、さまざまな「素材」に取り囲まれています。
けれど、その根っこのところで暮らしを支えているのは、何万年も前から変わらない「土」という素材なのかもしれません。
今回お話を伺ったのは、まさにそんな土と向き合い続ける陶芸家・吉野瞬さんです。
火と水、そして土を原資に、ときに土地の素材を生かしながら、ときには土地から軽やかに距離を取りながら制作に取り組む吉野さんの姿勢は、私たちがこれからの「暮らし」を考えるためのヒントを、静かに示してくれるはずです。
広島市西区の地下にひっそりと佇む、隠れ家のようなアトリエでお話を伺いました。
できるだけ少ない手数で、「土」を理想のかたちへ
――本日はよろしくお願いします! 今日も今まで作業していらしたんですか?
吉野さん:ちょうどさっきまで、マグカップに取っ手をつける作業をしていたところです。もうすぐ個展のために上海に行くので、それまでにキリのいいところまで仕上げておきたくて。
――素朴な質問なのですが、土を捏ねたり、ろくろを挽いたりしているときって、どんなことを考えているものなんでしょうか?
吉野さん:陶芸って、基本的には粘土を伸ばしてかたちをつくっていくんです。だからこそ表現できる滑らかさだったり、しなやかな美しさを僕は追求したくて。そのために大事になってくるのが、いかに手数を減らすか、ということです。
――あまり土に触らない方がいい、ということですか?
吉野さん:触れば触るほど、理想のかたちからは遠ざかってしまうというか。要するに粘土が伸びすぎてしまうんです。一度伸びてしまったものを縮めるのはすごく難しい。だからこそ、どれだけ少ない手数で完成形まで持っていけるのかを、いつも意識しています。
――それって、頭のなかで「理想のかたち」がはっきりと描けていないとできないことですよね。
吉野さん:そうですね。でも、だいたい80%くらいまで理想に近づけたら、そこで手を止めることが多いかもしれません。というのも、僕は作品によってスタイルをコロコロと変えるタイプなので。ひとつのスタイル、ひとつの理想を突き詰めていくよりも、新しい作品を100個、200個と生み出していく方が、僕にとっては面白いんです。
――ちょっと意外でした。陶芸家というと、他人には違いがわからないような細部をひたすら磨き上げていく、みたいなイメージを勝手に抱いていたのかもしれません。ちょっとでも気に入らない部分があると、パリーンッと割っちゃう、みたいな(笑)。
吉野さん:僕は全然そういうタイプではないですね。とにかく楽しみながらつくっていますから。正直にいうと、売れるかどうかはさておき、作品が窯から出た時点で、もう満足なんです。だから個展にいらしたお客さまにも「いかに楽しんでつくったか」をひたすら語っています(笑)。
何もない「地下」で、自分の内面を引っ張り出す
――あらためて吉野さんのキャリアも伺っていければと思うのですが、ご出身は広島でしたよね?
吉野さん:広島市の安佐北区の出身です。母方の実家が金物屋を営んでいたので、鍋だったり鉄瓶だったり、そういう暮らしにまつわる道具が身近にある環境でした。祖父や祖母は焼き物も好きだったから、盆や暮れに親戚が集まると、すっごい大きなお皿が出てくるんです。備前とか古伊万里とか波佐見とかの。それをみんなで囲むのが、子どもの頃の当たり前の光景でした。
――吉野さんの陶芸家としてのルーツには、そんな原体験があったんですね。
吉野さん:そうなんだと思います。それで美術科のある高校に進学して、あるとき、濱田庄司という陶芸家の本に出会ったんです。
――濱田庄司というと、民藝運動の中心的な担い手のひとりでもある益子焼の大家ですよね。
吉野さん:そうそう。その本のなかでは、濱田先生が世界中の民藝品を紹介していて。それにすごく惹かれたんです。美しくてきらびやかなものではない、日常のなかにぽつりとあって、歳月のなかで存在感を増していく――。それがとにかくカッコいいと感じて。自分も民藝の流れを汲みながら、焼き物のいろはを学びたい。そう思って、高校卒業と同時に、濱田先生を益子の工房に招き、ともに作陶した益子焼の窯元に弟子入りしました。
――益子での修行はどうでしたか?
吉野さん:親方は厳しかったけれど、技術だけではなく、本当にたくさんのことを教えてもらいました。でも、当時はとにかく一日も早く独立したかった。やっぱり、自分で自由に作品をつくれるようになりたかったので。だから8年の修行を終えて独立したときは、めちゃくちゃ嬉しかったですね。
――独立後、最初は因島にアトリエを構えられたんですよね。
吉野さん:ちょっとしたご縁があって、因島で海沿いの一軒家を借りられることになったんです。それでせっかくなら、何かこの土地ならではの素材を使えないかと考えるようになって。目をつけたのが八朔でした。実は因島って、八朔の発祥の地なんですよ。
――それは初耳でした!
吉野さん:島内の柑橘農家さんが、剪定した枝や葉を畑で燃やしているのを見て、その灰を釉薬に使えないかと思いついたんです。試してみたら、流れ方も色調も、すごく面白い釉薬ができて。僕の定番の技法として、今でも柑橘農家の方から定期的に灰を送ってもらっています。
――因島という土地と、吉野さんのものづくりが結びついていったんですね。
吉野さん:けれど誤解ほしくないのは、僕はあくまで陶芸家として、この灰でつくる釉薬そのものが好きなんだ、ということです。「島の名物」のようなものをつくりたかったわけではなくて。もっと言えば「この島の灰でつくったから、これはいいものなんです」という売り方をしたくはなかったんです。
――ある種のわかりやすいラベルで括られることへの抵抗感というか。
吉野さん:「瀬戸内海の作家」みたいなことを言われるのも、あんまり好きじゃなくて。青い色を使うと、瀬戸内ブルーだね、とか。もちろん、作品づくりに土地の影響がないわけではありません。でも、僕はもっと自分の内なるものを表現したかった。そのためには何にもないところ、自分の内面を引っ張り出さざるを得ないようなところに身を置くしかないと思った。それで今はこうやって、誰も寄りつかない地下のアトリエにこもっているわけです(笑)。
土は進化しない。土は限られている。だから尊い
――「場所にこだわらない」ということは、陶芸に用いる土の産地にもそれほどこだわりはないのでしょうか?
吉野さん:産地に強いこだわりがあるタイプではないですね。普段はつくりたい作品に応じて、大まかに三種類くらいの土を使い分けています。ただ、何かしらの意図を持たせたいときは、いつもは使わない産地の土をあえて用いることもあります。
――たとえば、どんなときですか?
吉野さん:2023年に開催されたG7広島サミットのワーキングディナーのために、テーブルウェアの制作を依頼されたことがありました。そのときに使ったのが、当時の岸田首相にゆかりのある東広島の土です。ろくろ挽きにも適したいい土で、機会があればこれからも使ってみたいなと思っています。
――「産地にこだわりはない」とはいえ、やっぱり土そのものには強い関心があるわけですよね。
吉野さん:そうですね。最近、あらためて感じているのが、陶芸の技術はどんどん進化するけど、土は進化しない、ということです。それは土が自然から与えられた素材だからにほかなりません。そういうどこまでも原始的・根源的な素材を使いながら、そこにいかに現代的な陶芸の要素をミックスさせていくのか。作家として、とても興味のあるテーマのひとつです。
――「土は進化しない」というのは、言われてみるとハッとしました。あえて伺ってみたいのですが、土という「進化しない素材」を使うことを、ある種の技術的な制約のように感じることはありませんか?
吉野さん:素材に限らず、3Dプリンターのような最新の技術を使えば、どんなかたちもつくれるんだと思います。それどころか、今はAIがデザインだってしてくれるのかもしれない。でも、そこに作り手の「気持ち」とか「魂」みたいなものを込めることができるのか。僕はやっぱり、難しいと思います。……もしできたとしても、それは縄文土器の時代から何万年も続いてきた「陶芸」という営みとは、もうまったく別のものになってしまう気がするんです。
――連綿と続いてきた陶芸という営みから外れてしまう。
吉野さん:だからやっぱり、僕はもっと「土から考える」ことを大切にしたい。土って、とても尊いものなんですよ。
――尊い、ですか?
吉野さん:粘土は、一度焼成するとセラミック化してしまいます。それはどんなに細かく砕いても、もとの土には戻らない。つまり土だって、有限の資源なんです。
――当たり前のものすぎて、土を「有限の資源」だと感じたことはなかったかもしれません。
吉野さん:その限りある資源を、陶芸家は使わせてもらっている。だからこそ、僕の作品はできるだけ生活のなかで使ってもらいたいんです。
――飾っておくだけ、ではなくて。
吉野さん:そうです。自然が何万年もの時間をかけて生み出した土という素材を、僕たちが加工する。それが日常の道具となって、「食べる」という行為を支え、ときには誰かをもてなすために使われていく。陶芸って、そういう営みだと思うんです。
つくる人とつかう人の、暮らしがつながる瞬間
――これまで、陶芸というのは土地に根ざしたローカルなものづくりだと思い込んでいた気がします。もちろん、そういう側面もあると思うのですが、お話を伺っていると、むしろ陶芸はすごく根源的で、だからこそ普遍的な営みなのだと感じました。
吉野さん:そういう意味では、僕自身も昔から、海外での活動を強く意識しています。先ほど名前を挙げた濱田庄司も、バーナード・リーチをはじめ、海外の作家と積極的に交流していました。世界にはそれぞれの国や地域ごとに異なる暮らしがあって、それにあわせてものづくりのあり方も自然と変わってくる。僕もそこに関心があるんです。
――海外で作品を発表するときに、意識していることはありますか?
吉野さん:「日本を背負う」みたいな感覚は、できるだけ持たないようにしています。「茶の湯」とか「抹茶」とか、わかりやすくてキャッチーではあるんですけどね(笑)。僕は日本に生まれた日本人ではあるけれど、そのバックボーンではなくて、ひとりの陶芸家としての自分を見てほしいんです。
――「瀬戸内の作家」と呼ばれたくなかったのと同じですよね。
吉野さん:そうですね。あとは海外で個展をひらくときには、一緒にワークショップもやるようにしています。たとえばメキシコで個展をするなら、メキシコシティとかオアハカとかトドス・サントスとか、いろんな都市を訪ねて、現地のアーティストと一緒にものをつくったり、話しをする機会を設けるようにしていて。「日本だとこういう作り方をするんだけど、そっちはどう?」みたいに。
――ある種の技術交換というか。
吉野さん:そうそう。外国に行かなくても、日本で国際協力プロジェクトに関わることも増えています。昨年の夏は、コロンビアやボリビア、キューバからウチに研修生が来ていて、1カ月弱くらい一緒に制作をしていました。こういう取り組みは、今後もっと増やしていきたいなと思っています。
――そういうかたちの国際協力もあるんですね。
吉野さん:本当に、いろいろな関わり方があると思うんです。たとえば、少し技術的な話になりますが、海外では粘土の研究がまだ十分にされていないことも多くて。そういう国では耐火性の低い土を使っているので、1250℃以上の温度で焼成すると、器が潰れてしまうんです。
――なるほど。
吉野さん:でも、それだと釉薬がうまく溶けない。だから南米の国などでは、低温でも釉薬が溶けるように鉛を加える手法が使われてきました。日本では安全面の理由から禁止されていますが、向こうではそれが当たり前だったんです。
――土の違いが、技術の違いにつながっているんですね。
吉野さん:もちろん土の違いはありますが、高温で焼ける“いい土”は南米にもあるはずなんです。だったら、それを生かせる方法を一緒に模索していきたい。そうやって陶芸、つまりテーブルウェアをよくしていくことって、ひいてはその国の食を豊かにすることにつながっていくと思うんです。
――器を変えることで、暮らしを少しずつ変えていける。
吉野さん:そう思います。ただ、それは僕が一方的に「教える」ということではなくて。僕も海外のアーティストから、いろいろなことを吸収したい。陶芸のこともそうですし、どういう食卓でどういうものを食べて、どんな暮らしをしているのか。そういうことを、もっと知りたいんです。あとはやっぱり、「土」そのものも気になりますし(笑)。
――やっぱり、最後は土なんですね。
吉野さん:海外に行くと、よくトレッキングにも出かけるんです。そうすると、僕はずーっと地層を見ていますからね。ちょっとだけ土を持ち帰っては、それで何かを焼いてみる。もっともっと世界中の土を焼いてみたいと思っています。
――本当に陶芸を楽しまれているんですね。まだまだ伺いたいことはたくさんあるのですが、最後にひとつだけ、このメディアの定番の質問を。吉野さんにとって、「暮らし」とは?
吉野さん:僕にとって陶芸は「仕事」じゃないんです。食事をするのと同じように、土と向き合いながら器をつくることが、暮らしの一部になっている。そうやって僕がつくった器が、誰かの暮らしをちょっとだけ心穏やかなものにしているのかもしれない。僕の暮らしと、それを使ってくれる人の暮らしが、そこでつながっていく。「僕はこういう暮らしをしているけど、あなたはどうですか?」というように。
「DoboX」で地形を見る