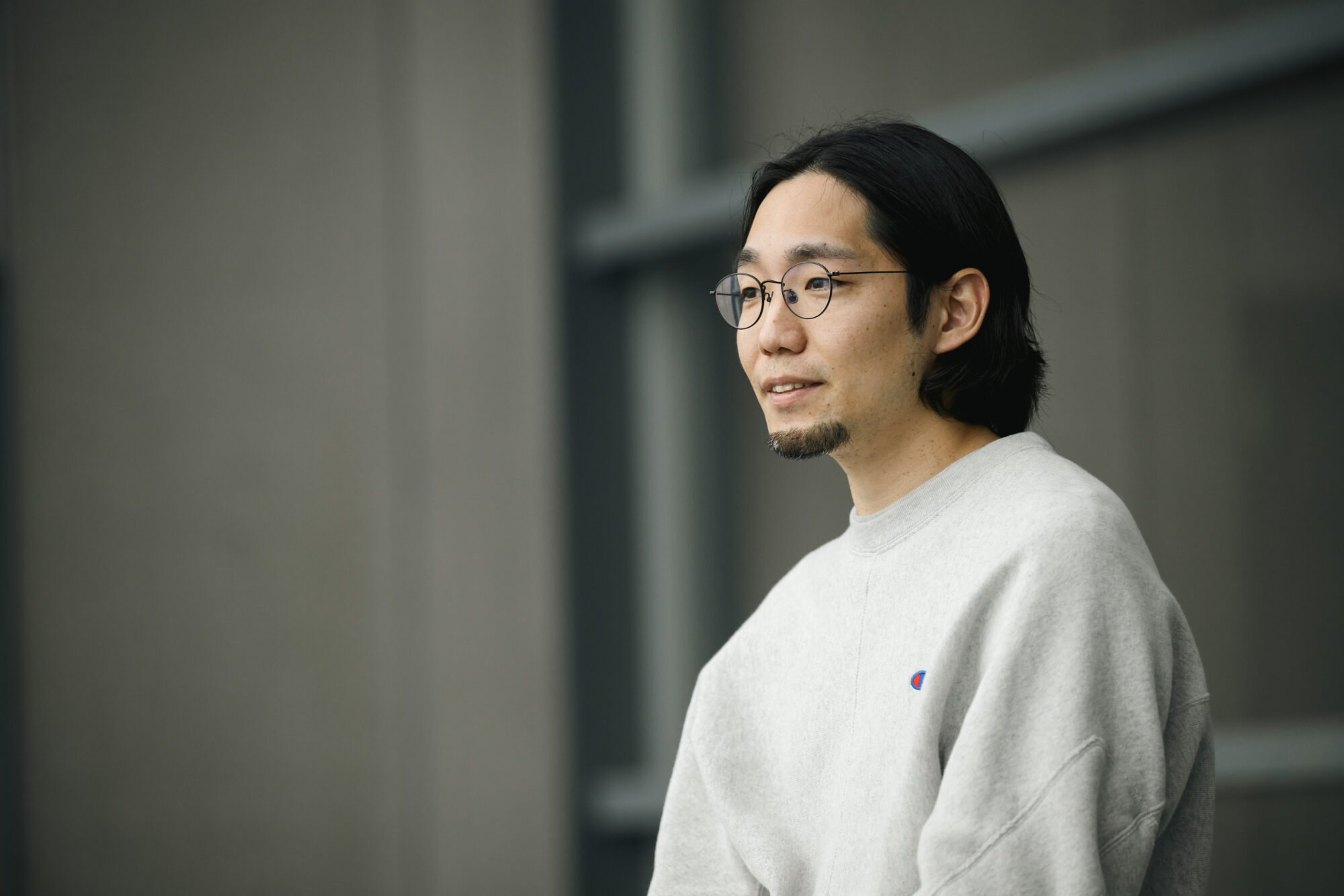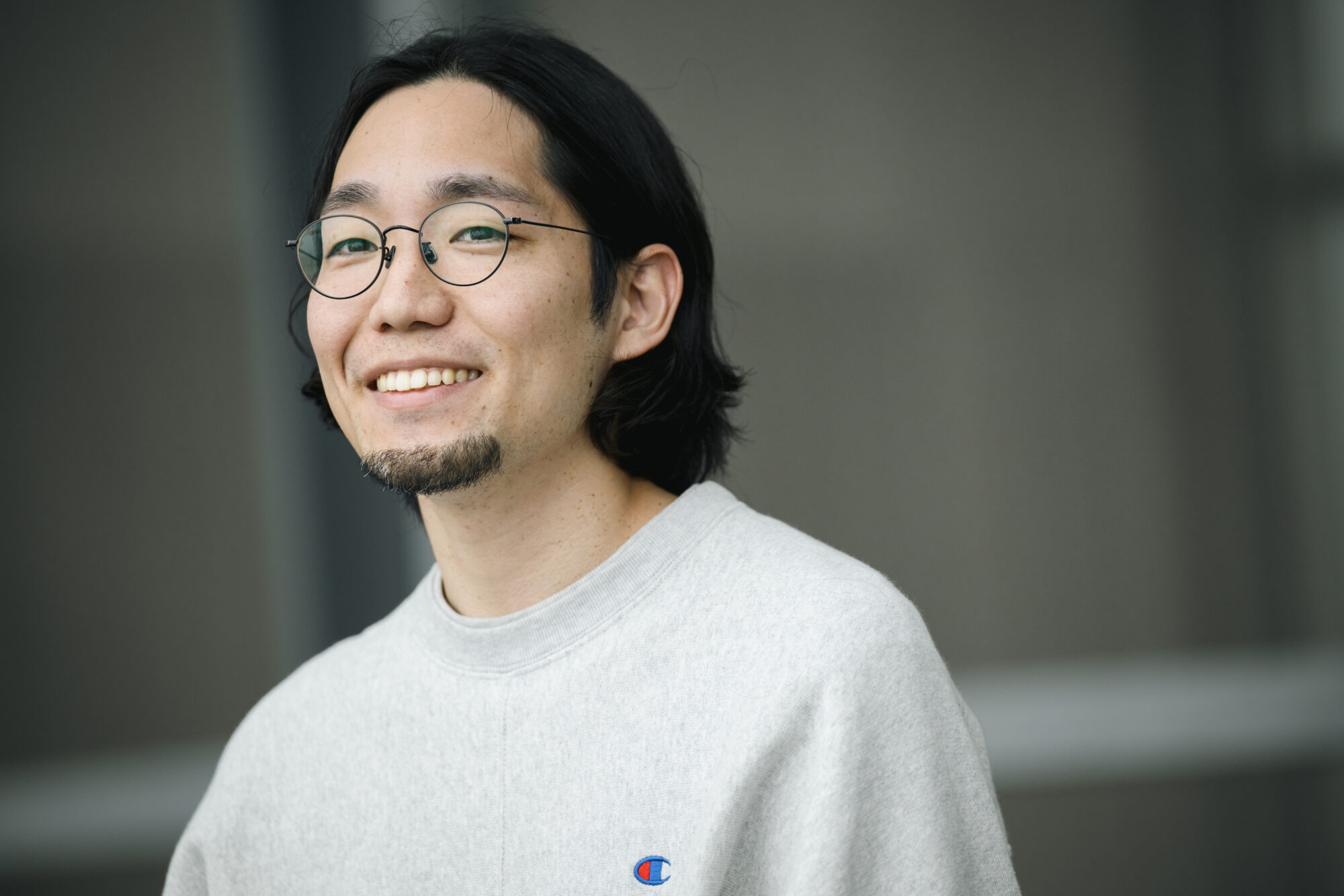広島のB面を描き出す。鈴木知悠が考える、街を楽しむ「勇気」とは 。
広島の「B面」の魅力を発信する『B-SIDE TRIP HIROSHIMA』。建築家・デザイナーの鈴木知悠さんが、地域の文化や暮らしをつなぐプロジェクトへの想いを語ります。
広島、浜松を拠点に地域資源の掘り起こしやまちづくり、設計などを行う。建築デザイン事務所+tic を共同主宰。現在は株式会社荒谷建設コンサルタントに籍を置き、様々な領域での活動を展開中。
カセットテープのケースをぱかりと開くと、なかにはカセットではなく『B-SIDE TRIP HIROSHIMA』と題された、小さな冊子が収められている。
江田島町切串の魅力を掘り下げた、このポップで不思議なリトルプレスを手がけたのは、建築家でデザイナーの鈴木知悠さん。広島の観光のB面(裏側)を盛り上げるプロジェクト『B-SIDE TRIP HIROSHIMA』の一環として制作されたものだと言います。ガイドブックからは取りこぼされてしまうような、広島のB面。そこに光をあてることで、何が見えてくるのか。土地のオリジナリティとは、そして本当の意味でのその土地の魅力とは。鈴木さんが敬愛する建築家・谷口吉生氏が設計を手がけた「広島市環境局中工場」でお話を伺いました。
広島という街の「切り口」の
豊かさに惹かれて
――中工場ははじめてなのですが、素晴らしいロケーションですね。鈴木さんにとっても、お気に入りの場所ですか?
鈴木さん:そうですね。ぼくは元々、建築家の谷口吉生さんが設計した建物、ということでこの施設を知ったんです。すぐ裏手には海があって、そこではお酒を飲みながら、釣りをしている人もいたりする。そういうのも含めて、この場所が好きなんです。ゆっくり考えごとをしたいときなんかに、ちょくちょく訪れています。
――建築は、ずっとお仕事として携わってきたんですか?
鈴木さん:建築の世界のど真ん中にいたわけではないのですが、大学卒業とともに友人と建築デザイン事務所を立ち上げて。静岡県の浜松市を拠点に設計をしたり、家具をつくったり、内装工事をしたり。空き家をシェアハウスにリノベーションして、それを自分たちで運営する、といったこともしていました。今も普段は、広島市内の建設系のコンサル会社で働いています。
――ちなみに浜松にはどんなご縁が?
鈴木さん:大学が浜松だったんですよ。土地と自分の関係性でいうと、僕自身の出身は神奈川で、両親はふたりとも東京出身。小さい頃には山梨にも住んでいたので、「ここが自分のルーツだ」と強く感じる土地はあまりなくて。今こうやって広島にいるのも、流れ着いたというか、旅の途中のような感覚です。
――でも広島以外にも選択肢はたくさんあったわけですよね。
鈴木さん:東京や大阪はさておき、それなりの規模のある都市の方が、自分のスキルを生かせそうだなというのが、まずは前提としてありました。そのなかで広島を選んだのは、直感もあるのですが――。広島を語るキーワードってたくさんありますよね。それこそ「平和」とか「野球」とか、「路面電車」とか。そうかと思えば海も山もすぐ近くにあって、谷口吉生や丹下健三といった偉大な建築家が設計した建物も点在している。そういう「切り口」の多さに惹かれたのかもしれません。このフィールドなら、自分も色んなことができるんじゃないか、と。
B面に息づく、地域と人の魅力を掘り起こしたい
――『B-SIDE TRIP HIROSHIMA』では、広島のなかでも江田島町切串という土地にスポットを当てています。
鈴木さん:切串って、本当に広島市の目と鼻の先にあるんです。でも、広島市の人たちが日常的に訪れる土地かというと、そんなことはなくて。じゃあ、そのふたつをつなげることができたら、観光で広島を訪れた人はもちろん、県内で暮らしている人たちにとっても、オルタナティブな提案になり得るんじゃないかと思ったんです。
――「B-SIDE」というコンセプトも、すごく面白いと思いました。
鈴木さん:「B-SIDE」という名前にはB面、つまりA面の裏側にある、知る人ぞ知る地域の魅力を届けたい、という想いを込めています。たとえば、切串には大歳神社という神社があるのですが、その謂れが面白いんです。宮島の厳島神社を建てたときに、余った木材で建立された、と言い伝えられていて。今も厳島神社の管絃祭というお祭りにあわせて、切串でもお祭りをやっているんです。
――厳島神社というと、まさに広島のA面のひとつですよね。
そうなんです。そしてその裏には、今もこうやってA面とは別のかたちで、地域の人たちの暮らしや伝統が息づいている。そういう意味でも「B-SIDE TRIP 」という企画のプロトタイプとして、切串はぴったりの場所だったと思っています。
一人ひとりのひらめきを、
自然に受けとめる街であってほしい
――鈴木さんがこれをどういう人に届けたいと思っているのかも、すごく気になりました。たとえば、広島のB面の魅力を、県外の人に発信したいのか。それとも広島県内の人たちに届けたいのか。どちらですか?
鈴木さん:僕自身のモチベーションは、どちらかというと後者に寄っています。というのも、街を楽しむことって、地元の人にとってもある種の「勇気」というか、きっかけみたいなものが必要だと思っていて。たとえば、ここの海岸でお酒を飲みながら釣りをすることって、ある人にとっては当たり前でも、別の人にはちょっと勇気がいることのような気がするんです。
――「やってみたいな」と思っても、それを実行するにはちょっと勇気がいるというか。
鈴木さん:今でもすごくよく覚えているのですが、僕が広島に来たばかりの頃、仕事帰りに歩いていると、同僚が「ちょっとそこのベンチでお酒でも飲まない?」と誘ってくれたことがあって。ベンチに座って川を眺めながら、ふたりでコンビニのビールを飲んだんですけど、その感じがすごく良かったんですよ。「川」と「コンビニ」と「お酒」を、パッとつなげるその回路に、ちょっとカルチャーショックを受けたというか。
――たしかに、東京の街中とかだと、あまりできないことかもですね。
鈴木さん:ある場所で生まれる、ひとり一人のちょっとしたひらめきみたいなものを、自然に受けとめてくれる街が、やっぱり僕は好きなんです。ただ、そのためには勇気だったり、ある種のリテラシーも必要だと思っていて。だからこそ『B-SIDE TRIP』では、「この場所では、こういう過ごし方もできるんだよ」という視点を、広島で暮らす人たちにも提案できたらいいなと思っています。
「ついで」をつなげることが、
暮らしの楽しみになっていく
――そうした地域に根ざした活動をしている一方で、鈴木さん自身は移住者というか、やっぱり地元の人から見たら「外から来た人」でもあると思うんです。そのことに、さびしさみたいなものを感じることはありませんか?
鈴木さん:うーん、さびしいと思うことは、そんなにない気がします。ただ、僕は広島にまったく知り合いがいなかったので、会う人会う人に「この街のおすすめはどこですか?」とか、「どこかいいお店を知りませんか?」と聞きまくっていて、それを全部Google Mapにまとめているんです(笑)。それはもちろん情報収集のためでもあるのですが、新参者がこの街に溶け込むための術になっている部分もあるのかもしれません。
――今の活動も、それに通じるものがあるかもしれませんね。『B-SIDE TRIP』としては、何か今後の展望はありますか?
鈴木さん:ただ単に広島の各地域を紹介していくというよりも、それぞれの土地をゆるやかにつなげるプラットフォームのようなものをつくれたらと思っています。広島のなかでも地域ごとに、まだまだ本当に地元の人しか知らないような「B面」はたくさんあると思うので。今はほとんど僕ひとりで動いているプロジェクトですが、『B-SIDE TRIP』というコンセプトに共感して、一緒に動いてくれる仲間や、自治体さんが出てきてくれたら、すごく嬉しいです。
――このメディアでも、何か鈴木さんとご一緒できたら嬉しいです!
鈴木さん:ぜひぜひ。これをご縁に、いつでもお声がけください。
――ありがとうございます。それでは最後の質問です。鈴木さんにとって「暮らし」とは何でしょう?
鈴木さん:直接的な答えにはならないかもしれませんが、最近、僕がすごく意識しているのが、暮らしのなかでいかに「ついで」を楽しむか、ということです。映画を観に街に出たら、じゃあついでにここの和菓子屋さんでいちご大福を買って帰ろう、とか。日常なかで、そういう点と点とがつながっていくと、きっと僕たちの暮らしは、もっと楽しくなっていくような気がしています。